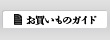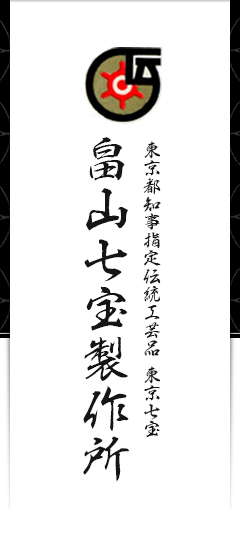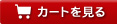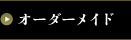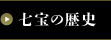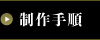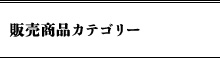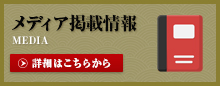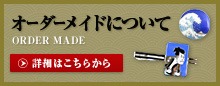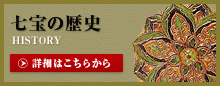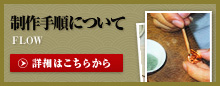アイテム別に紹介!伝統工芸の技が光る七宝焼きの値段について

日本には、刺し子、薩摩切子や焼き物など、さまざまな伝統工芸があります。確かな技術を持つ職人によって作り出される伝統工芸品は、見た目の美しさだけでなく、使い長く愛用できる実用性も兼ね備えているのです。そんな優れた伝統工芸品の中でも「七宝焼き」は、古い歴史を持ちながらも、現代に適したアイテムが多く取り扱われています。
しかし、伝統工芸品は高価なイメージがあるため、安いアイテムを購入すると失敗するかもと気になる方もいるかもしれません。そこで今回の記事では、伝統工芸の七宝焼きが高価な理由から、アイテム別に値段について紹介します。
七宝焼きの値段が高い理由
日本が誇る伝統工芸の一つである「七宝焼き」は、世界を虜にするほど優れた技術で作られており、人々を魅了しています。気が遠くなるほどの時間をかけて作られているため、値段が高いアイテムが多くあるのです。ここでは、七宝焼きの値段がなぜそれほどまでに高く設定されているのか、その理由を見ていきましょう。
原材料の高騰による影響
七宝焼きは、「金」「銀」「胴」などの金属を材料に用いているため、世界情勢の価格高騰によって値段が高くなる傾向が続いています。もともと金は産出量が少なく、昔から希少な金属として扱われているのです。また、七宝焼きの色付けに使う釉薬(ゆうやく、うわぐすり)は、珪石や硝石などの主原料に金を混ぜることで「赤色」、銀を混ぜると「黄色」になります。
このように、金などの金属を材料として用いる七宝焼きだからこそ、原材料となる金などの高騰は、アイテムの価格を押し上げているのです。
1高い技術で手間ひまかけている
七宝焼きに限らず、伝統工芸品は職人の手仕事によって作られるため、高い技術力が必要になります。職人が一人前になるまで数年かかりながらも、一つのアイテムを作り上げるまでにも手間ひまかけているのです。七宝焼きは独自の高い技法はもちろん、いくつもの工程があるため時間も手間もかかってしまい、大量生産ができないのも価格が高くなる原因と言えるでしょう。
丈夫で長持ちして使い続けられる
七宝焼きの魅力の一つでもある「色合いの多さ」が、長い年月を経ても色あせないのが、優れた技術力を感じさせます。宝石のように美しい輝きを失わない丈夫さから、ツタンカーメンのラピスラズリ、日光東照宮の飾りなどに用いられているのです。このように七宝焼きには、長い時間が経過しても色あせることのない技術が施されているため、長持ちして使い続けられることから「高価なモノ」としても評価されています。
【アイテム別】七宝焼きの特徴と値段について
七宝焼きは「高級品」の扱いになっているため、手軽に購入できないケースもあります。しかし、アイテムによっては気軽に七宝焼きを楽しむこともできるのです。ここでは、アイテム別に七宝焼きの特徴と値段について紹介します。
ネックレス・ペンダント
シンプルなワンピースなどに華やかさをアップしてくれる七宝焼きのネックレスやペンダントは、色合いはもちろん、キラキラと輝くツヤを兼ね備えているので、ジュエリーなどのアクセサリーに引けを取りません。何と言っても七宝焼きは好みのデザインを反映させることができるため、有名な絵画などをペンダントに落とし込むことができます。そのため七宝焼きには、ジュエリーには表現できない美しさがあるのです。
ネックレスやペンダントの相場は7,000円くらいになりますが、アイテムによっては手軽に購入できる5,000円から、贅沢なデザインが施されている40,000円くらいもあります。
和物ブローチ・ピンズ
七宝焼きならではの「色とツヤ」を持ちながらも、さまざまな形やモチーフをブローチやピンズにして身に着けることができます。愛らしい「ふくろう」をはじめ、動物好きにはたまらない「犬」や「猫」などをモチーフにしているモノもあり、襟元やバックなどにおしゃれアイテムとして活躍してくれるのです。七宝焼きは手作業になるため、ひとつひとつの色や表情が異なります。
そんな七宝焼きのブローチやピンズは1,000円くらいの手軽なアイテムからありますが、5,000円くらいからが多く、高価なアイテムでは100,000円以上からあるのが特徴です。
ハレの日に最適な飾皿
古くから伝わる伝統工芸品の七宝焼きは、その優れた技術力は世界からも高く評価されています。そんな魅力的な七宝焼きを「飾皿」に仕上げたアイテムがあり、ハレの日の贈り物に最適です。さまざまな絵柄がありますが、金色の空を背景にして2羽の鶴が舞い、雄大な富士と松が描かれたアイテムは、縁起が良いとされています。大切な日の記念品としても、海外へのお土産にもおすすめです。
サイズやデザインにもよりますが、3,000円~200,000円と値段の幅も広めになります。
まとめ

七宝焼きは高価なアイテムとして認知されていますが、まったく手がでない価格帯ばかりではありません。七宝焼きは価格が高い傾向もありますが、質の良いアイテムとして長く使い続けることができます。アイテムによりますが、値段は3,000円くらいから数万円、高価なモノで数十万円になるでしょう。
値段が多少高くても丈夫で長持ちできるため、長い目でみたら安いかもしれません。良いモノを長く持ち続けられる優れた伝統工芸品として、七宝焼きは今も多くの方に愛用されているのです。
「畠山七宝製作所」では、紀元前からの伝統を受け継いでいる伝統工芸の七宝焼きを提供しております。オリジナルアイテムはもちろん、お客様のご要望にお応えするオーダーメイドも承っており、確かな技術を堪能していただけるでしょう。七宝焼きにご興味がございましたら、ぜひ当製作所までお気軽にお声がけください。